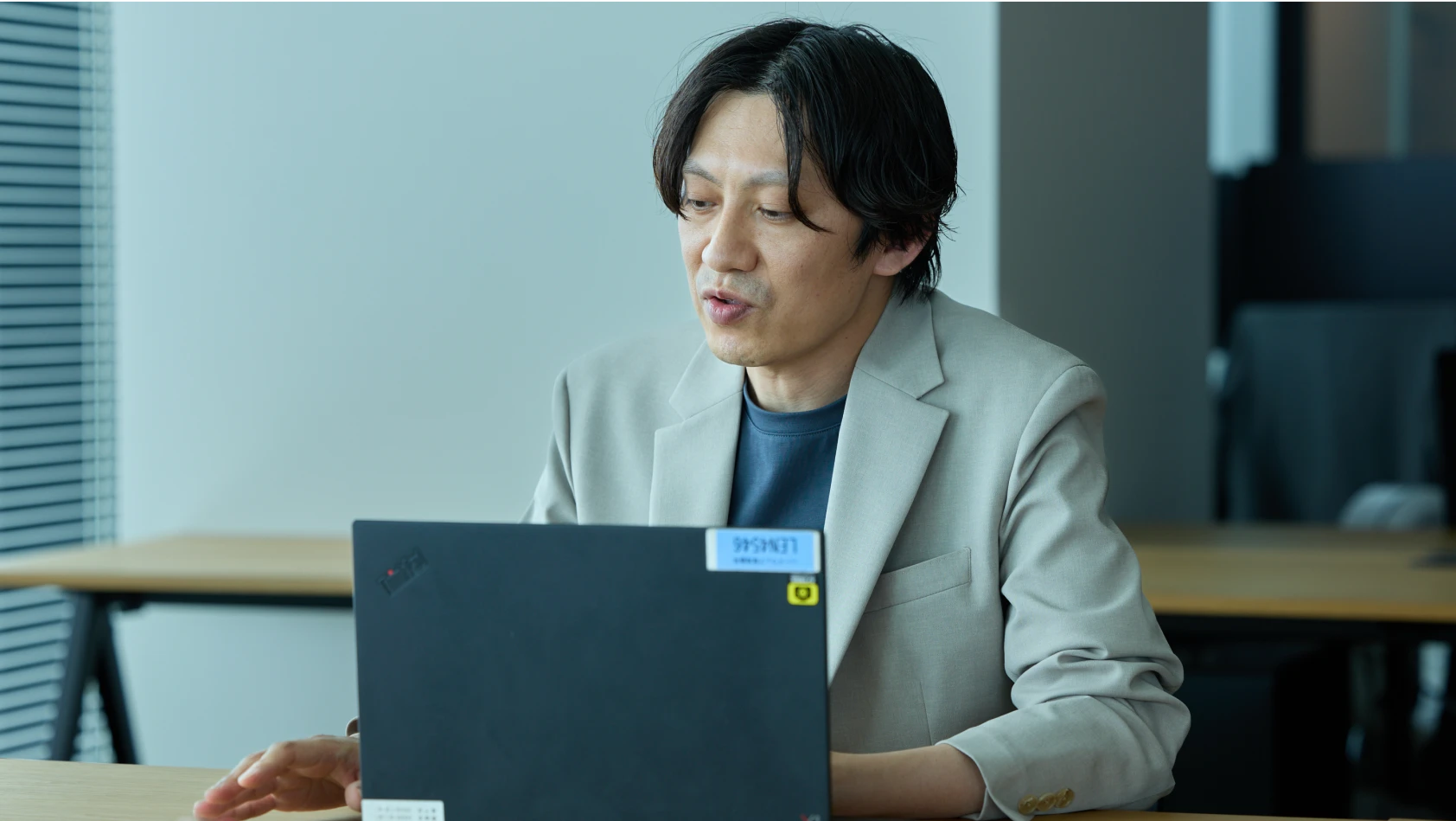──エンジニアにとって、SUBARU Labの魅力とは?
SUBARU Labに集まっているメンバーは、非常に個性的で面白い人たちばかりです。アルゴリズムのエキスパートがいたり、データ収集や分析のプロフェッショナルがいたり、優れた自動車運転技術を有する人もいます。AIの分野は進歩のスピードが速く、短期間にたくさんの論文が出るのですが、そうした先端の論文を大量に読み込み、丁寧にリサーチを行っている同僚もいて、尊敬しています。さまざまな分野で高いスキルを持った人財が集まっていることは、大きな刺激になります。メンバーの国籍も多様で、私自身は海外とのやり取りはしませんが、日常的に海外とやり取りしているメンバーもいます。
逆に、SUBARU Labにいないのは、何かやろうとしたときにやる前から否定するようなタイプの人ですね。ここには、「とりあえずやってみたらいい」と考える人たちが集まっています。大きな予算を要するものについては、もちろん正当な手続きを踏みますが、障壁は決して高くありません。やろうと思ったことを、実行に移しやすい環境です。
個人的には、スライド資料を作成する時間が少ないことが魅力ですね。資料作りに時間をかけるよりも、手を動かすことに集中できます。そのため、実際に手を動かしたいエンジニアにとっては、非常に良い環境だと思います。