スリッパを30メートル跳ばせ!『魔改造の夜』に挑んだメンバーが想いを語る座談会

スリッパを30メートル跳ばせ!『魔改造の夜』に挑んだメンバーが想いを語る座談会
記事内の日付や部署名は、取材当時の情報に基づいた記述としています
仕事は違っても「笑顔をつくる」という想いでつながる「SUBARUびと」。今回は、エンジニアたちが日用品や家電製品を「魔改造」してモンスターマシンに仕立て、そのアイデアやテクニックを競技形式で競うNHKの人気番組『魔改造の夜』に挑んだ、山川さん、大木さん、上田さん、荒川さんの4人が激動の1カ月半を振り返ります。プロジェクトの詳細は、『魔改造の夜』特設サイトをご覧ください。
目次

山川 大地(やまかわ だいち)さんモノづくり本部 パワートレイン生産技術部
2002年に入社。第3生産技術部、パワーユニット生産技術部、電動車両生産技術部を経て、2025年より現職。入社以来一貫して、パワートレイン部品に関する生産技術業務に従事。現在は、生産性向上のための業務効率化や自動化にも取り組む。『魔改造の夜』では、ガス噴射機構の開発を担当した。

上田 朋久(うえだ ともひさ)さん技術本部 車両安全開発部
2017年に入社。車両研究実験第2部を経て、2025年より現職。入社以来、主に悪天候時の視界性能やランプ類の夜間視界性能の開発に携わり、現在も0次安全*1に関する性能開発に従事。『魔改造の夜』では、ガス噴射機構の開発を担当した。
https://www.subaru.co.jp/outline/about/zeroaccident/
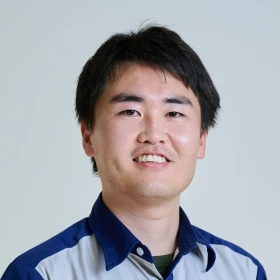
大木 巧(おおき たくみ)さん航空宇宙カンパニー 航空宇宙技術開発部
2019年に入社。航空宇宙カンパニー自律システム設計部を経て、2023年より現職。入社以来一貫して、無人航空機の開発に携わり、現在は無人航空機用AIの技術開発に従事。『魔改造の夜』では、飛行シナリオの設計とガス噴射機構の開発を担当した。

荒川 紀香(あらかわ のりか)さん経営企画本部 デザイン部
2021年に入社し、現在の職場に配属。入社以来一貫して、クルマの外装デザインの造形検討やクレイモデル制作に従事。『魔改造の夜』では、試作機製作とロゴデザインを担当した。
厳しい重量制限、目標は30メートル飛行できるスリッパ
―― 最初に「スリッパ跳ばし」というお題を聞いたときの、率直な気持ちを教えてください。
- 上田 :
- 貴重なチャレンジだと思う一方で、不安が大きかったです。「スリッパを30メートル跳ばしたチームは優勝」(複数のチームが30メートル跳ばした場合は、共に優勝とする)というルールがあったため、「30メートル跳ばす」ことを目標に掲げたものの、実現できるイメージが湧きませんでした。
- 山川 :
- たった60グラムのスリッパ、これが難題でしたね。「生贄(魔改造前のスリッパ)より重くなってはいけない」「必ず動力機構をつけなければならない」というルールがあり、正直、進め方の見当がつきませんでした。
- 大木 :
- お題を聞いた時は、単純に羽をつけて跳ばせば良いのではないか、と思っていました。しかし、60グラム以下のスリッパにする必要があると知った瞬間、これは無理だと思ってしまうほど、重量制限が厳しかったです。

目指したのは、「人を中心としたモノづくり」
―― スリッパの魔改造は、どのように始まったのでしょうか?
- 荒川 :
- まずは、実際にスリッパを跳ばしてみましたよね。
- 上田 :
- そうですね。チーム全員でスリッパ跳ばしをしてみると、たとえ同じ人であっても、毎回蹴り方とスリッパの跳び方にバラつきがあって、蹴り方によってスリッパの挙動や跳び方が大幅に変わることがわかりました。このことから、「人間の動作に左右されない仕組みを作るべきだ」と考えるようになったのです。
- 大木 :
- 自然と「人を中心としたモノづくり」を実践していましたよね。SUBARUらしさを感じました。
- 上田 :
- 魔改造開始当初から「蹴りやすさ」が大事なキーワードになり、最終的には「誰が蹴っても30メートル跳ばせるスリッパ」を目指して、SUBARUが持つ航空宇宙技術の知見も生かそうと決めました。

白熱した議論、定まらない方向性
―― 跳ばす仕組みが決定するまで、どのように検討が進みましたか?
- 山川 :
- スリッパを跳ばすための機構を議論し始めると、チーム全員から溢れるほどアイデアが出ました。
- 大木 :
-
私は普段、航空分野の業務に従事していることから、魔改造期間の途中でブランコチーム*2からスリッパチームに移籍しました。スリッパチームに来た当初、羽ばたき案で翼を展開している人たちと、射出案でガスロケットを開発している人たちがいて、最終的に1つのマシンにまとまるのか不安を覚えました。
- NHK『魔改造の夜』で「ブランコ25m走」に挑戦したチーム
『魔改造の夜』 ブランコ25m走
- NHK『魔改造の夜』で「ブランコ25m走」に挑戦したチーム
- 上田 :
- 私と山川さんは、ガスロケットを動力とする射出案を担当していました。射出技術を確立するためには、確かめないといけないことがとにかく多く、トライを重ねて検証する必要がありました。しかし、それらの検証を同時並行して進めるには時間が足りなかったです。
- 山川 :
- ひたすら試作機を作って、試していましたよね。あの怒涛のトライ&エラー、私は結構楽しかったです。
- 大木 :
- この時点では、案ごとの技術開発が進んでいて、全体最適の道筋が見えてこなかったです。
- 山川 :
- 途中、口喧嘩ともとれるような、白熱した議論もありましたね。
- 上田 :
- あの議論は、チーム全員のプライドと熱量の証です。言いたいことを言える環境であったことは、チームの雰囲気や開発スピードに良い影響があったと思います。アイデアを秘めたままにならず、常に情報がオープンで、チーム全員が本音で話し合うことができました。そして、議論したことを「まずはやってみよう」と、試しながら前に進んでいきました。
- 大木 :
- やはり、考えるだけではモノは出来ません。「考えながらモノを作り、試行し、試行から学び、学んだことから考え、またモノを作る」というサイクルが大事だと改めて思いました。
- 上田 :
- 魔改造期間が後半になるに従って、そのサイクルが高速で回っていました。一つひとつの小さい成功体験を積み上げて、それをチーム全員で共有し、どこへでも進める状態から、着実に進むべき道を選んでいった感覚です。
- 荒川 :
- そうでしたね。色々なアイデアが徐々に絞られ、それぞれに試作が進んでいった後、本命案として、「射出案」と「羽ばたき案」の開発が進みました。

苦渋の決断を経て、チームが結束
―― 長い試行錯誤の中で、マシンの方向性が決まるきっかけとなった転機を教えてください。
- 荒川 :
- 転機は、「羽ばたき案を断念する」という決断でした。魔改造期間内に必要部品を調達することができず、どうしても形にならないため、断念せざるを得なかったのです。あの時の悔しさは今でも覚えています。
- 大木 :
- 夜会当日の2回ある試技では、射出案と羽ばたき案で跳ばしたいと考えていました。羽ばたき案は、技術的に手応えがあったため、技術以外の理由で諦めざるを得なかったことが非常に悔しかったです。
- 山川 :
- 本当に苦渋の決断でした。1カ月以上かけて挑戦してきたマシンを諦めなければいけないわけです。自分が羽ばたき案のメンバーだったらと思うと、逃げ出したくなるほど苦しい瞬間でした。
- 上田 :
- 驚いたのは、羽ばたき案を担当していたメンバーの切り替えの早さです。「射出で勝とう」とすぐに頭を切り替えて、これまで羽ばたき案の開発で培った知見を、射出案に持ち込んでくれました。その姿には、本当に感動しました。
- 荒川 :
- チーム全体が、熱くなりましたよね。結果的に、羽ばたき案で検討していた翼や飛行時の重心に関する知見は、射出案の飛行安定性の検討に役立ちました。あの悔しさは、決して無駄ではなかったと言えます。
- 大木 :
- 羽ばたき案を担当していたメンバーの1人が、「羽ばたきは諦めるけれど、勝つことは諦めない」と言っていたことが印象的です。
- 上田 :
- 苦しい瞬間だった一方で、チーム全員が他人事にならず、ひとつになった出来事でした。「こうなったら絶対に射出式スリッパで勝ちたい!」と強く思いましたね。チーム全員が、立場や役割の壁を超えてひとつのモノをつくっていました。

―― マシンの方向性が見えた後、どのように魔改造を進めましたか?
- 大木 :
- とにかく、重量の壁をクリアすることから考えました。ガスロケットのカートリッジを搭載することで、スリッパ全体の60グラムのうち、30グラムを占めてしまいます。残り30グラムで、翼も各種機構も組み込まなくてはといけません。
- 上田 :
- 軽量カートリッジも試しましたが、推力が足りなくて使えなかったのです。重量を抑えると性能が落ち、性能を上げると重量オーバーしてしまう。常にそのジレンマとの戦いでした。
- 荒川 :
- 私は、生贄として提示されたスリッパらしい形や色にもこだわりました。生贄からかけ離れた見た目で優勝したとしても、SUBARUを代表して挑戦する以上、そのプライドが許せないと思ったからです。射出案は、ソール部分にガスロケットやその他の機構を埋め込むことができたため、「普通のスリッパ」に近い形を維持できました。ただ、生贄のスリッパの色に塗装する場合、塗料分の重さがプラスされてしまいます。塗料の数グラムを捻出するため、チーム全員で他の機構の軽量化に取り組み、何とか60グラムに収めることができました。
- 大木 :
- 見た目にもこだわりつつ、翼の位置や重心などを何度も計算して試しました。その結果、ガスロケットが働かなくても、普通に蹴れば跳ぶスリッパ、誰が蹴っても跳ぶスリッパが完成しました。
- 上田 :
- しかし、納品1時間前に射出口のパーツが壊れてしまったのです。原因は、強度不足でした。結局、本命の機構は使用できず、予備の機構に切り替えて夜会に臨みました。スリッパの修復はできましたが、不安な気持ちを抱いたまま夜会当日を迎えました。

射出式スリッパの名前は『ブルーコメット』*3
- モンスターマシンの詳細は、『魔改造の夜』特設サイト「スリッパ跳ばし 技術解説」をご覧ください。
https://www.subaru.co.jp/difference/makaizo/swing/
スリッパが空中に蹴り出され、息を呑んだ数秒間
―― 夜会当日を振り返って、いかがでしたか?
- 上田 :
- リーダーの阿部さんがスリッパを蹴り始めてから、ガスが噴射するまでの約1秒が、本当に長く感じました。「ガスが出なかったらどうしよう」という不安から、体感的には5秒くらいに感じたほどです。現実では、ガスロケットのカートリッジに穴が開く理想的な音がして、スリッパが遠くに跳び、心の底から安堵しました。
- 山川 :
- 1試技目に記録を残せたことで、ひとまずの安心感がありました。この成功があったからこそ、2試技目に向けても自信が持てたと思います。
- 大木 :
- 跳んだ瞬間は、やはりうれしかったです。ただ、どんな形でガスが噴出したのかをすぐに確認していましたね。喜びよりも、改善点に目がいきました。そこはやはり、エンジニアの性だと思います。

仲間との挑戦、そしてSUBARUらしさの追求
―― 『魔改造の夜』への挑戦を終えて、どんな学びや気づきがありましたか?
- 山川 :
- 失敗から得られるものが、こんなにも大きいのだと感じる経験でした。魔改造期間の1カ月半、私は数々の失敗をしました。そこでふと、普段の仕事では、失敗しないように立ち回ることが多いことに気がついたのです。「失敗はした方が良い」とよく聞きますが、その通りだと実感することができました。自分で上限を決めずにチャレンジし、失敗から得たものによって、今後も継続的に成長できると思います。まずは自分から実践することで、周囲にも良い刺激を与えたいです。
- 大木 :
- 私も、「失敗を許せる、誰もが挑戦できる風土」を作っていきたいと思いました。『魔改造の夜』の作業部屋では、一見、魔改造に関係ないことをやっていそうに見える人もいましたが、誰もその作業を止めませんでした。どこかで結びつくかもしれないと、チーム全員が同じ目標に対して、何らかの作業をやっていたからこそのことです。その結果、多くのアイデアが出て、成功につながったのだと思います。
- 上田 :
- 立場や役割を気にせず、すべてに対して自分事として捉えて議論できたことは、大きな経験でした。SUBARUの人が集まると、それぞれの技術を持ち寄り、スピード感を持って課題をクリアできることがわかりました。普段の業務においても、何事も自分事として捉え、さらにポジティブな議論を活発にしたいです。それによって、より良いモノづくりができると思いました。
- 荒川 :
- 私は、横のつながりを強く感じました。言いたいことを言い合える、横の人たちが何をやっているかが分かる環境を経験でき、すごく良かったです。隣の人がしている作業に、自分がどう関わることができるか、能動的に考え、動くことができました。この経験を活かし、今後も、自分の仕事だけではなく、隣の仕事を覗いて、自分にできることはないかを考えながら仕事をしていきたいと思いました。
- 上田 :
- 魔改造期間は何回も心が折れて辛かったのにもかかわらず、不思議と「終わってほしくない」という感覚がありました。
- 大木 :
- 何をつくるかではなく、この仲間とこの場所で没頭できることに楽しさを感じていたのだと思います。「やっていることは違うが、やりたいことは全員一緒」という雰囲気を、普段の業務にも広げていきたいですね。

―― 最後に、『魔改造の夜』への挑戦で感じたSUBARUらしさを教えてください。
- 山川 :
- 誰もがチャレンジすることに前向きなことです。魔改造中は、チーム全員で何度も失敗しましたが、すぐに改善点を考えて、着実に前進していました。この風土こそ、SUBARUの強みだと思います。
- 大木 :
- 私が考えるSUBARUらしさは、「人を中心としたモノづくり」です。この考え方が自然に身についていることこそ、SUBARUらしさであり、SUBARUの強みだと感じます。モノを作ってからお客様にとっての使い勝手を考えるのではなく、設計する段階から徹底的にお客様のことを考える。この意識が、SUBARUで働く全員の根底にあると思います。
- 荒川 :
- やはり、「人を中心としたモノづくり」です。『魔改造の夜』参加を通じて、徹底的にお客様目線で考えるという意識が、全員に根差しているのだと改めて実感できました。
- 上田 :
- 私も、皆さんが言う通り、「人を中心としたモノづくり」だと思いましたが、それに加えて、個人の役割にとらわれず、全員でモノづくりができることも、SUBARUらしさだと感じました。全員がモノづくりに向き合い、真剣な議論を交わした先に良い商品が完成し、お客様や社員の笑顔をつくることができると、改めて実感することができました。

白熱した議論を交わし、仲間とともに「人を中心としたモノづくり」を徹底した「SUBARUびと」。ぜひ、次回のコラムもご期待ください。

