学生フォーミュラ支援活動 Vol.2
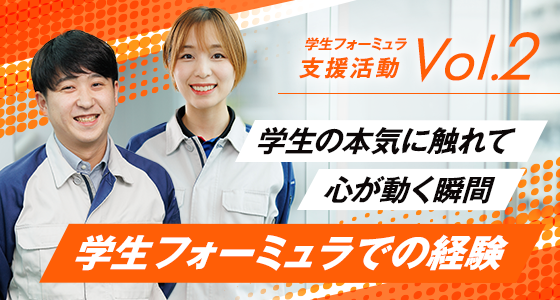
学生フォーミュラ支援活動 Vol.2 メンバーが語る学生フォーミュラでの経験
記事内の日付や部署名は、取材当時の情報に基づいた記述としています
仕事は違っても、「笑顔をつくる」という想いでつながる「SUBARUびと」。 様々な部署で働く「SUBARUびと」を、仕事内容や職場の雰囲気を交えてご紹介します。今回は、学生が自ら構想・設計・製作した車両で、モノづくりの総合力を競うモータースポーツ「学生フォーミュラ」の支援活動について紹介した記事Vol.1に続き、当社の学生フォーミュラ支援WG(ワーキンググループ)メンバーである森さんと榮さんに、自身の学生フォーミュラでの経験やWGの支援活動について聞きました。
学生フォーミュラ支援活動 Vol.1の詳細は、こちらをご覧ください。

森 彩香(もり さやか)さん車両環境開発部 品質第三課
2019年に入社。パワーユニットの市場データを分析して課題を抽出し、改良の早期着手を促す役割を担う。学生フォーミュラ日本大会にSUBARUの企業ブースを出展するにあたり、説明スタッフとして参加。その後、学生フォーミュラ支援WGの活動に賛同し、メンバーに加わる。

榮 祐世(さかえ ゆうせい)さんパワートレイン設計部 電動ユニット設計第一課
2022年に中途入社。電気自動車のeAxle*1の性能設計を担当。学生フォーミュラのEVクラスで審査員を務めたことがきっかけで、SUBARUの学生フォーミュラ支援WGの存在を知り、活動に参加。
目次
同じ競技でも
チームや人によって
経験が異なる
お二人とも、学生時代に学生フォーミュラに参加されていたとのことですが、当時はどのような活動をしていましたか?
- 森:
- 私はチーム内でサスペンションの設計・製作を担当し、セッティング出しも含め、幅広い工程に携わっていました。学生フォーミュラでは、1台の車両をチーム全員で完成させるため、サスペンション以外の製作にも自然と関与する機会が多くありました。当時、作業していた工場には、金属や樹脂などの材料を加工するプログラム制御式のフライス盤(工作機器)が設置されており、学生のうちから、本格的なモノづくりに取り組む貴重な経験を積むことができたと思います。
- 榮:
-
私は学生フォーミュラがやりたい一心で、卒業課題として競技活動が認められている大学へ進学しました。しかし、入学の年にその教育課程が廃止となり、当初の計画通りには進められない状況となりました。
そこで、方向転換を図り、当時国内でもまだ数が少なかったEVチームを自ら立ち上げ、4年間にわたりチームリーダーとして活動を継続しました。ゼロからのスタートでしたが、仲間と試行錯誤を重ねて形にしていった経験は、今の業務にもつながる大きな糧になっています。

あきらめない力と
俯瞰する視点が
今につながる
学生フォーミュラの経験が、現在の業務に活きていると感じる点はありますか?
- 森:
- 現在、私はパワーユニットの市場課題に対応する業務を担当しており、原因の特定に時間を要する複雑な不具合に向き合う場面も少なくありません。そのような業務において、学生フォーミュラで培った「最後までやり抜く力」が大きな支えとなっており、技術者としての成長にもつながっていると実感しています。学生フォーミュラの活動は、予期せぬトラブルが日常的に発生し、問題を解決するために粘り強く取り組む姿勢が求められる環境でした。そうした経験を通じて、困難に直面しても諦めず、試行錯誤を重ねながら解決策を見出す力を養うことができたと感じています。
- 榮:
- 現在、私はEVの駆動ユニットであるeAxle*1の開発に携わっており、eAxleシステム全体の性能設計を担当しています。学生時代にチームリーダーとして全体を俯瞰しながら活動していた経験が、業務において非常に役立っていると感じています。車両として成立させるためには、個々の部品単位ではなく、全体的なバランスを把握しながら設計を進める必要があります。社内外の関係者と連携しながら調整を行う場面も多く、学生フォーミュラで培った「全体を見渡す力」が、現在の業務を進める上での大きな助けとなっています。
- 森:
- 確かに、一つの要素だけが良ければそれで良いというわけではなく、何かを変更した際に他の部分へどのような影響が及ぶかを常に意識する視点は、学生フォーミュラの活動を通じて自然と身についたように思います。
- バッテリーEVなどモーターを主動力とするクルマの「走る」ために必要な主要部品を1つにまとめ、パッケージ化したもの。主にギア、モーター、インバーターといった部品から構成される。

学生の本気に触れて、
心が動く瞬間
現在取り組んでいる、学生フォーミュラ支援WGの具体的な活動を教えてください。
- 森:
- 支援活動では、SUBARU側から講習会の開催を提案することもあれば、学生の皆さんから「このような内容を教えてほしい」といった具体的な相談をいただくこともあります。大会では、デザイン審査や車検などの評価項目が設けられているため、それらに向けた事前のアドバイスや確認を希望されるケースもあります。そうした要望には、できる限り柔軟に対応しながら、学生の皆さんが安心して取り組める環境づくりを進めています。
- 榮:
-
私たちの支援活動では、実践的な学びの場を提供することを心がけています。たとえば安全講習会は、SUBARUの工場施設を利用し、作業中に起こり得るヒヤリハットを実際に体験していただき、安全に対する考え方を育む場としています。
学生の皆さんとの対話を通じて、その真剣な姿勢や熱意に触れるたび、大きな刺激を受けています。学生の皆さんが揺るぎない信念を持って、疲れを忘れるほどに集中して取り組む姿は、情熱が今もなお自分の原動力であることを実感させてくれます。そして、その情熱を業務に注ぎ続けたいという思いが、いっそう強くなります。

学生の「学び」に
寄り添い続けたい
今後、学生フォーミュラ支援活動をどのように発展させていきたいと考えていますか?
- 森:
- 現在は、支援活動として安全講習やドライビング講習などを実施していますが、それに限らず、学生の皆さんの学びに寄与できるような技術的な内容にまで支援の幅を広げていきたいと考えています。たとえば、SUBARUが強みとする四輪駆動の制御に関する講座など、フォーミュラカーづくりに直接関係する内容ではないかもしれませんが、将来的に何らかの形で役立てていただけるような知見を提供したいと考えています。技術を伝えることを通じて、学生の皆さんが新たな視点を得るきっかけとなればうれしく思います。
- 榮:
- 今は、支援活動に強い関心を持つメンバーが中心となって取り組んでいますが、今後も学生の挑戦を継続的に支えていくためには、社内で活動の意義を共有し、協力者を募りながら、組織的な支援体制を整えていくことが重要だと感じています。こうした体制づくりが、活動のさらなる発展にもつながると考えています。

学生フォーミュラ支援活動WGのメンバー(写真:左から榮さん、清水さん、森さん)
最後に、学生フォーミュラに打ち込む皆さんへ。
- 森:
- 学生時代は、チーム内で何度も議論を重ねました。外から見ると、まるで口論しているように映ることもあったかもしれません。しかし、そうした議論を通じて互いを理解することで、チームの絆が深まり、より良い車両づくりにつながっていったと感じています。社会に出ると、立場や経験の異なる人たちと協働する機会が増えますが、そうした環境の中でも、自分の考えを丁寧に伝えて共感を得る力は大きな武器になります。学生のうちに様々な人と意見を交わす経験を積んでおくことで、周囲を巻き込みながら前に進める力を養ってほしいです。
- 榮:
- 私は、車両制作よりもチームの立ち上げや体制づくりに専念していましたが、今振り返ると、それもまた他の人には得がたい貴重な経験だったと感じています。一つのことに真剣に向き合えば、必ず何かしら得られるものがあり、それは将来的に自分自身の財産となります。今はぜひ、思い切り熱中してほしいです。
学生フォーミュラへの支援に情熱を注ぐ「SUBARUびと」。ぜひ、次回のコラムもご期待ください。


