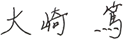CEOサステナビリティメッセージ
SUBARUグループを取り巻く状況
現在、自動車業界は100年に一度の大変革期と言われる転換点を迎えています。加えて、地政学リスクや主要国のインフレ、そしてSUBARUグループにとって重要な市場である米国の政権交代など、自動車業界やSUBARUグループにとってだけでなく、社会全体にとっても先行きの不透明感が増している状況です。しかしこのような不確実な状況であるからこそ、ステークホルダーの皆様からのSUBARUグループに対する期待はより一層高まっていると感じます。私たちは、SUBARUグループの事業の成長だけでなく、それを社会の持続可能性に結びつけていくために何ができるのか、これまで以上に深く考え、独自の価値を示すことが求められる局面に立っています。
SUBARUグループの持続可能な成長と地域社会との関わり
SUBARUグループの成長と社会の持続可能な発展を結び付ける接点として、二つのことを重視しています。ひとつは「SUBARUとお客様との絆」、もうひとつは「ひとつのSUBARU」です。
・SUBARUとお客様との絆
私はSUBARUとお客様の関係は、単なるメーカー・販売会社と消費者の関係を超えた特別なものだと感じています。その象徴的な例が、米国におけるSubaru of America, Inc.(SOA)の「Love Promise」です。Love PromiseとはSOAと全米のSUBARU販売特約店の活動のことで、慈善団体と連携し、環境保護や地域支援などの活動を展開しています。この活動の特徴は、お客様自身と販売店、そしてSUBARUの三者が共に地域社会の課題に取り組めることです。例えば、お客様がSUBARU車を購入する際に、ご自身の関心に沿った慈善団体を選び、SUBARUがその団体に寄付を行うという年に一度のキャンペーンを行っています。SUBARUは2025年の米フォーブス紙の「社会へ良い影響をもたらす企業ランキング」で米国内3,000を超えるブランドの中、3位に選ばれました(2023年、2024年はともに2位)。この評価の理由のひとつとして、Love Promiseの活動を通じた全米各地の地域コミュニティへの貢献があると考えています。SUBARUグループは、まず自動車メーカーとしてお客様にSUBARU車をご愛顧いただくこと、そしてお客様とSUBARUの絆を社会の持続可能性につなげ、お客様の人生に寄り添った存在になることを目指しています。また、これは日本国内でも同様です。国内で展開している販売特約店とSUBARUの取り組み「一つのいのちプロジェクト」においても、今後はLove Promiseと同じくお客様とSUBARU、そして社会との接点になる活動に発展させたいと考えています。
・ひとつのSUBARU
もうひとつの柱が「ひとつのSUBARU」です。これは従業員や関係会社だけではなく、お取引先様も含めた全体での連携を意味します。その一環として、私はこれまで社内の開発・製造などの組織の壁を取り払い、部署を越えた対話を活発化させてきました。さらにはお取引先様にもこの取り組みに加わっていただき、共に様々な検討を進めています。日本国内においては、SUBARU群馬製作所の近隣地域で多くのお取引先様が事業を展開されています。この物理的な距離の近さは、私たちの強みであり、SUBARUグループが地域社会と密接に連携しながら、共に成長していくための基盤です。今後は、物流・販売も含めたサプライチェーン全体で連携を深め、持続的な成長の可能性を広げていきたいと考えています。
2024年度のサステナビリティの進捗状況
2024年度、SUBARUグループは、これまでの「CSR重点6領域」を「サステナビリティ重点6領域」に発展させました。この見直しの目的は、企業として社会課題を解決するCSR視点に加え、SUBARUの価値や強みを一層活かした形で、SUBARUグループと社会の持続可能性に貢献していくことです。「サステナビリティ重点6領域」の「ありたい姿」は時間軸を設けずに、より普遍的な方向性を示すものとしました。その実現に向け、「重点テーマ」「目標」「KPI」を設定し、各取り組みを強化していきます。これによりSUBARUグループがサステナビリティに真摯に取り組んでいくという決意を、社内外に改めて発信できたとも考えています。
重点6領域:安心
「安心」の目標としてグローバルで「2030年死亡交通事故ゼロ※1を目指す」を掲げています。この目標へ向けた取り組みを着実に進めていくために、「SUBARUが市場に導入した最新技術による死亡交通事故※2への対応率」をKPIとして設定しました。
「乗る人すべてに、世界最高水準の安心と安全を」という総合安全思想に基づき、より厳しい事故形態への対応についても課題として認識し、取り組んでいきます。
今後は、SUBARUグループとして社会全体の交通事故ゼロの実現のために何ができるのか、そのためにどのような方策があるのかなど、より広い視点での課題にも向き合っていきたいと考えています。
- ※1
- SUBARU車乗車中の死亡事故およびSUBARU車との衝突による歩行者・自転車などの死亡事故ゼロを目指す
- ※2
- 交通ルール違反や相手側の著しい危険な行為がともなう事故などを除く
重点6領域:ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン(DE&I)
SUBARUグループの強みは「人」です。私は従業員全員が多様な個性を最大限発揮し活躍できる組織こそが、変化に強く、イノベーションを生み出し、持続的成長を可能にする組織であると考えます。これまでに、全ての従業員の多様な価値観を尊重するとともに、様々な個性を持つ従業員にとって働きやすい職場環境の整備を進めてきました。その取り組みの一つとして、「女性管理職者数」をKPIに設定し、「2025年度末までに2021年比で2倍にする」という目標を掲げていましたが、これについては2025年4月時点で既に達成しています。このことを受け、次なる目標として「2030年までに女性管理職100人以上」とすることを決定しました。SUBARUグループで働く女性が自らのキャリアにおいてありたい姿を実現し、充実した会社員生活を送れるようにすること、そしてSUBARUグループで働きたいと希望してくださる女性の方々が増えることを目指します。さらに、これは女性に限った話ではありません。社内には色々な「種」を持った従業員がたくさんいます。そのような人財を育て、イノベーションにつなげると共に「ひとつのSUBARU」にも発展させていきたいです。
重点6領域:環境
これまで「環境アクションプラン」として社内で推進してきた取り組みのうち、「気候変動の抑制」「サーキュラーエコノミーの実現」「自然との共生」を重点テーマとして設定しました。「気候変動の抑制」については、製品のライフサイクル全体でのカーボンニュートラルを目指すことも掲げています。SUBARUグループのバリューチェーン全体におけるGHG排出の大部分を占めるスコープ3、特に「販売した商品の使用」における排出削減に向けては、電動技術の市場への投入を重要な施策と位置付けています。2024年度には、SUBARU独自のストロングハイブリッドシステムを搭載した国内向け「クロストレック」、国内および米国向けの新型「フォレスター」を発表しました。BEV(バッテリーEV)については、2026年末までにSUV4車種、2028年末までにさらに4車種を加え、合計8車種の市場投入を予定しています。市場投入予定のバッテリーEVのうち、2025年4月には、トヨタ自動車株式会社との共同開発の第2弾として新型「トレイルシーカー」を、7月には第3弾の新型「アンチャーテッド」を公開しました。電動自動車・ハイブリッド車など多様な選択肢をお客様に提供しながら、「柔軟性と拡張性」を持って、環境目標の達成に向けて取り組みを進めていきます。
ステークホルダーの皆様とともにシナジーを起こす
私は、商品やサービスを通じてお客様や地域社会の皆様とつながり、その人生を豊かにしていきたいと考えています。また、一緒に社会の課題を解決していくうえでSUBARUを光り輝くブランドにしたいと思っています。
そのためには、お客様や地域社会の皆様からの共感に基づく協働が不可欠です。SUBARUグループの価値観を共有し、それぞれが持つ知見・技術・経験を掛け合わせることでシナジーを生み出し、「笑顔をつくる会社」を実現できると考えます。SUBARUグループに関わる全ての人々の笑顔を原動力に、愉しく持続可能な社会の実現と、SUBARUグループの持続可能な成長を目指していきます。
代表取締役社長 CEO